もともと書くことには時間がかかっていた私
アメリカで大学院生として生活を始めて5年目、日本陶磁器産業振興会(JAPPI)への投稿文を書くのが今年で3年目になる。果たしてこんな大学院生の一人ぼやきに誰が興味を持ってくれるのだろうと思いつつ、私自身アメリカ生活を振り返る良いきっかけとなっているため機会をいただけることをありがたく思っている。ありがたいと言いつつも、いつも締切ギリギリ(というより、場合によっては過ぎて)の提出になってしまう。
なぜ書くことにそんなにも時間がかかってしまうのか。指導教授の言葉で表現すれば、書くということは思考を整理する作業が9割以上を占める。実際目にする文字に起こす作業は1割にも満たない。それと共に書くということには感情労働が伴う。書き始めれば瞬く間に「これでいいのだろうか」「書いていることに意味はあるのだろうか」などと焦りと自分に対する疑いが忍び込む。「書く」という作業が「好き」と言える人は個人的には信用ならないと考える程、その作業は苦痛であると感じている。英語でpulling teethという言い方があるが、まさに「歯を引っこ抜く」程の痛みが伴う作業だ。
この焦りや疑いは私特有のものではない。何かしら書くことを一度は試みたことがある人であれば、皆必ず通る道のりだ。ベテランの作家でも同様に書くことの難しさに直面する。レストランに関する批評を毎月雑誌に掲載しているある作家は書き始める時には「もう終わりだ。今度こそは書けない。昔のタイピストとしての仕事に戻るしかない」と毎月のことにもかかわらず焦り始めるという。
しかし、書くことに対する恐怖心が全員共通して抱いているものだと気づくのにはだいぶ時間がかかった(ここまで読んで頂いた方々はなぜ、こんなにも長々と「書く」ことについて文字数を費やしているのか、とうとうネタ切れなのかと思っているかもしれない。もう少しだけ、お付き合いいただければと思う)。
日本にいた頃、朝早くからオフィスに閉じこもり、夜遅くまでいても一言も論文を書けないことがよくあった。とにかく書けない。当時は自分がだらしない人間なんだ、研究への情熱が足りていない、皆はできているのだからやはり自分が研究に向いていないのだ、などと自分を責めていた。でもいくら自分を責めても、書けることはなかった。行き詰まりを感じながら、どうすればいいか分からずもがき苦しんでいた。
アメリカの大学院には、学生が書くことをサポートするシステムがある
アメリカの大学院に行ってから、その認識は一変した。書けない自分を責めるのではなく、どのようにして自分が成功できるかのシステムを構築することに力を注ぐべきだということに気づいた。
アメリカでは「書くことは難しい」という前提で、その問題をどのように解決すべきか、様々なサポートシステムがある。私の場合は、一時期、書くことにつきまとう不安が膨れ上がり、どのように作業を開始すればいいか分からず、予定を立てること自体困難だったこともあった。ちょうどアメリカに来た直後で、諸々うまくいかず、自信を失っていた時に当てはまるかもしれない。
その時はAcademic CoachとWriting Coachという学業と書くことに関連する様々な面をサポートしてくれるコーチにお世話になり、予定を一緒に考えてもらった。本当に言葉通り一緒に付き添って考えてもらった。それもかなり詳細にだ。何時にどこで何を始めるか、予想される中断要因とそれに対する対応策、どれぐらいの仕事量が適切か、などとできる限りスムーズに事が運ぶように一通り話し合いが行われた。
|
実際のWriting Centerのホームページ (下) と、セッションの様子 (右)。 |
 |
 |
|
「個人」が耐え忍ぶことが美徳の日本、「社会システム」の不備に着眼するアメリカ
なぜこの話をするかというと(長々とお待たせしました)、この事例は単純に「書く」ということだけでなく、大きく言えば日米における社会システムに対する態度の違いにも通じるものがあると感じるからだ。
日本では大きく根性論だったり、耐え忍ぶことが美徳とされる面がいまだにあると感じている。それは自分自身もそうだったからよく分かる。苦しみから生まれるものがあるとは今でも思うが、しかしそれだけでは限界がある。
根性論とまで言えなくても「郷に入れば郷に従え」というような、その場のルールに適応することが強く求められる社会の中では、個人が抱え込まなければいけない負担が大きくなる。何かしらなし得ることができないと、その個人が弱いから、何かしらの素質が足りていないからなど、着眼点は「個人」になってしまう。結果として、より大きな社会的システムの不備とその解決策に関する議論を阻む。
アメリカでは社会問題の原因を個人に帰するのではなく、より大きなシステムに訴えかけることが多い。実際、一人の大学院生が辞めていく際、彼は辞めざるを得なくなった苦言のメールを全大学院生に向け送った。その内容は、大学院生に向けたサポートのなさを指摘し、学科全体の変革を求めるものだった。
それに対しての院生の反応は素早いものだった。すぐに院生全体の会議が開かれ、次のステップとして、各学年から代表一人を決め、学科の先生方に向けた嘆願書を作成した。嘆願書には、大学院生の給料を上げることや先生方のアシスタントとして働く際の業務の明確化など、様々な要求が記載された。嘆願書をもとに、全大学院生に向けた先生方との話し合いも行われた。そのスピードと嘆願書の洗練された内容に驚いた。
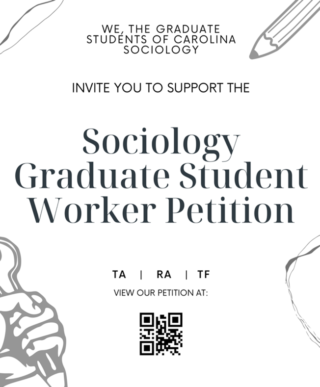 |
大学院生が作成した嘆願書への支持を求めるチラシ。 嘆願書は記載されているQRコードから見ることができ、実際に嘆願書を広く周知できるよう、チラシ配りや教員に対するロビー活動への協力をお願いする内容となっている。 |
もちろん、声をあげやすいとは言え、声をあげ続けなければいけない社会にも大いに問題はある。「アメリカはサポートシステムがたくさんあってすごい」と素直に感嘆していたところ、ウルグアイ人の友達に「でもそもそも、そのサポートシステムが存在しなければいけない社会に問題がある」とばっさり切り捨てられた。確かにその通りだろうと思う。しかし、日本と比べれば変革を要求しやすいのだろう。
社会システムによる問題解決をしようとするアメリカと個人の力でなんとか乗り切ろうとする日本、こんな所に「世界デジタル競争ランキング2022」で日本は29位と過去最低で低迷する原因があるかもしれない。日本政府は「デジタル庁」を発足するなど躍起になっているが、個人のマインドを変えるには相当の時間が必要に思う。
※ 本稿の筆者、村瀬里紗氏は、OBACの海外コラボレーターで、University of North Carolina, Chapel Hill, Department of Sociologyに在籍

