皆様、こんにちは。私は2013年から6年半、中国で仕事をしていました。はじめは、日本の会社から出張で出かけていましたが、2016年に現地の会社へ1年出向しました。その後、中国国有企業に転職をしました。就労ビザ取得のために、中国で初めて健康診断を受けたときに、日本との違いに驚きました。今回はそんな、中国での健康診断について、私の経験をご紹介します。
1. まるで「おちょこ」のような採尿容器
中国赴任の手続きのために、会社から指定された医療センターを訪れたときのことです。私にとって、中国の医療機関を訪れるのはその時が初めてでした。受付で言われるままに身長、体重を測り、採血をして、「次は尿検査」と言われて渡されたのが、小さな検尿容器でした。
 40ml位の容量なので、「おちょこ」と同じ位の大きさでしょうか。手のひらにすっぽりと収まる位の小ささです。紙コップでしか採尿したことがない私は、「これ、どうやって採るのだろう?」と、その小ささに面食らいました。
40ml位の容量なので、「おちょこ」と同じ位の大きさでしょうか。手のひらにすっぽりと収まる位の小ささです。紙コップでしか採尿したことがない私は、「これ、どうやって採るのだろう?」と、その小ささに面食らいました。
汚い話で恐縮ですが、想像してみて下さい。「おちょこ」位の大きさの検尿容器です。溢れたら嫌だし、飛びはねても嫌だし、コントロールが狂って容器を持つ手に尿がかかっても嫌です。腹圧を微妙にコントロールしながら、めちゃくちゃ慎重に採るしかありません。しかも、トイレは洋式タイプではなく、日本で言う「和式」タイプです。しゃがむという動作だけでも辛いのに、その辛い体勢で腹圧をコントロールし、見事に小さな容器の中に収めなければならないのです。
トイレに入って、検尿容器の蓋をとりました。でも、蓋の置き場所がありません。仕方なく、トイレットペーパーホルダーのわずかな平面を見つけて、滑り落ちないように慎重に蓋を置きました。そして、微妙に腹圧をコントロールしながら慎重に採尿し始めたのですが、容器が小さすぎて、どれ位の量なのか見えません。途中で止めては、容器を確認することを繰り返しました。適当な量を採ったあと、こぼさないように慎重に蓋をかぶせ、採尿を完了しました。尿検査でこんなに疲れるとは思ってもみませんでした。
こんな容器を使うのは、この病院だけかと思っていたら、そうではありませんでした。
翌年、別の病院へ検査に行ったときも同様な容器を渡されました。紙コップは漏れの危険があるからなのか、理由はよくわかりませんが、蓋つきの小さなプラスチック容器がデフォルトのようです。
2. 効率重視?!検査台では靴を脱がなくてOK
 心電図やエコー検査を受ける時、日本では靴を脱いで検査台にあがるのが普通です。いや、靴を脱がないと怒られますよね。ところが、私の行った中国の医療センターでは、靴を履いたままでOKなのです。検査台に上がろうと、靴を脱ごうとしたら「そのままでいい」と言われてビックリです。
心電図やエコー検査を受ける時、日本では靴を脱いで検査台にあがるのが普通です。いや、靴を脱がないと怒られますよね。ところが、私の行った中国の医療センターでは、靴を履いたままでOKなのです。検査台に上がろうと、靴を脱ごうとしたら「そのままでいい」と言われてビックリです。
さらに驚いたのが婦人科検診です。
中国の国有企業に勤めるようになってから、毎年健康診断を受けさせてもらっていたのですが、日本の人間ドックに近い内容の健康診断で、婦人科の内診もあったのです。その内診を受ける時、靴を脱いで、履いていたズボンをおろそうとしていると、中国人の先生が何かわめいていました。
「大勢待っている人がいるから、早くしろっていうことかな?」
私が焦りながらズボンをおろしていると、カーテンの向こうから通訳の女性が、「片方だけでいいって先生が言っています」と教えてくれました。
最初私は、「片方だけでいい」の意味がわかりませんでした。そのとき私はズボンをはいていたのですが、どうやら片足だけ脱げばよいという意味だったようです。でも、片方だけ脱ぐ方が、全部脱ぐより面倒くさいです。
しかし、先生は内診に使う器具を手に持ちながら、せきたてるように何かを叫んでいます。私は仕方なく、ズボンも下着も右足だけ抜いて診察台にあがりました。左足の足首あたりにズボンと下着が丸まっています。
診察が終わり、左足に丸まった下着とズボンを履くのに、またモタモタしてしまいます。下着の向きが回転したりして履きづらいのです。慌てて診察台をおり、ズボンのファスナーを上げながら、通訳の女性に「片方だけ脱ぐって、逆に難しいよね」と言うと、彼女は苦笑いをしながら「そうですよね」と返してきました。
医療センターには大勢の受診者が詰めかけていましたから、回転を速めるための措置なのでしょうか。 日本の健康診断とは随分と違う様子でした。
3. ビッグデータをもとに提案された健康対策とは
健康診断を受けてから4日後、ネットで検査結果を確認できると通知がありました。日本と比べて随分と早いです。受診の際に割り当てられた番号とパスワードを入力すると、2種類の資料がアップロードされていました。
ひとつは8ページに及ぶ検査結果、もうひとつは14ページもある「分析資料」でした。この「分析資料」とは、私の検査結果をビッグデータに照らして分析したものです。私の健康状態が、同じ年齢の女性と比べてどの程度の位置づけにあり、将来どのような病気のリスクがあるのか、グラフを交えて詳細に説明されていました。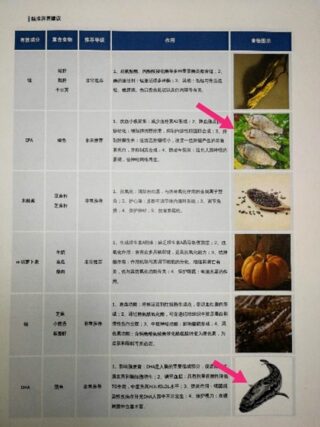
さらにページを繰っていくと、食事に関する提案が出てきました。これまた細かに、1日の総摂取カロリーの内、炭水化物はいくらで、タンパク質はいくらでと、内訳まできっちり数字で示されているのです。
さらに、食品群別の推奨摂取量が何グラム、推奨するビタミンの摂取量はどれくらいかまで、事細かに書かれています。さらに読み進めていくと、オススメの食品とその写真が載っていました。
コレステロール値の高い私には、EPAやDHAなどの成分摂取が望ましいと書かれており、代表的な食材として、フナと雷魚の写真が掲載されていました。
マグロやサンマ、イワシのような海水魚ではなく、淡水魚で例が示されるところが、いかにも中国らしいです。ひょっとしたら、私が住んでいたのが、内陸部にある四川省成都市だったからなのかもしれません。
次に出てきたのは、運動の提案でした。私の場合、「散歩なら4キロメートル、水泳なら28分、縄跳びなら14分やればよい」と書かれていました。
 さらには、どの筋肉をどうやって鍛えたらよいのか、図解付きで説明されていました。たとえば、「プランク」だったら、「1日1回、毎回13分やればよい」というように具体的に時間まで記されています。そのほかにも、28分とか14分とか13分とか、なぜこんな半端な数字なのかと思いましたが、これこそビッグデータからはじき出された数字の証拠かもしれません。
さらには、どの筋肉をどうやって鍛えたらよいのか、図解付きで説明されていました。たとえば、「プランク」だったら、「1日1回、毎回13分やればよい」というように具体的に時間まで記されています。そのほかにも、28分とか14分とか13分とか、なぜこんな半端な数字なのかと思いましたが、これこそビッグデータからはじき出された数字の証拠かもしれません。
日本と比べて圧倒的な母数を持つ中国。そのビッグデータが示してくれた私への提案は、実はとんでもなく有用なのかもしれません。中国の健康診断は、終わってからが面白いと思いました。
皆さんも、もし中国に赴任して健康診断を受ける機会があったら、こんな提案を受け取ることがあるかもしれません。もし受け取ったら、ぜひ試してみてください。

